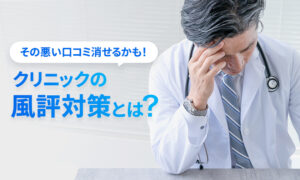クリニック開業のススメ
クリニックの開業の成功に向けた現場で役立つ実践的な情報を提供します。
クリニックに有効な集患方法とは?オフラインマーケティングの活用

クリニックの安定した経営を目指すには、来院患者数の確保が重要です。
確保の手段として、いまの時代は、インターネットマーケティングが主流となっていますが、依然としてオフラインマーケティングも有効な手段に変わりません。
オフラインマーケティングとは、インターネットを使わない従来のマーケティング手法であり、テレビやはがき、屋外看板、ダイレクトメールなどが含まれます。これらを上手く活用し、オンラインマーケティングと掛け合わせることで、さらなる集患の効果が期待できますので、クリニックでの活用方法について以下で確認していきます。
安定経営には来院患者数の確保が大事
クリニックの安定した経営には、毎月の来院患者数が一定あり、診療報酬による収入が経費や借入金の返済、家計としての生活費などの支出を上回ることが重要となります。
なお、手元資金(キャッシュフロー)が黒字であっても、中期的に来院患者数が減少している場合は、経営が安定しているとはいえません。そのため、来院患者数の確保はクリニックの経営を安定して持続させる上で最も重要な要素となります。
この点を踏まえながら、安定した経営を実現し、継続するために活用するマーケティングによる集患ポイントを確認していきましょう。
マーケティングの目的は「認知」と「集患」
まず、クリニック開業時におけるマーケティングの目的には、
「認知度を高める」こと、「集患する」ことが挙げられます。
安定経営のため、いまの時代はインターネットマーケティングが主流となっていますが、オフラインマーケティングも依然として有効な手段であることに変わりません。特に、地域密着型のクリニックや、高齢者などインターネットをあまり利用しない層へのアプローチをする際には、非常に効果的となります。
オフラインマーケティングとは?
オフラインマーケティングとは、インターネットを介さずに行う従来型のマーケティング手法を指します。具体的には、テレビやチラシ・はがき、屋外看板、電車広告、地域情報誌、ダイレクトメールなどを活用した方法が含まれます。
これらのオフラインマーケティング手法を活用することで、地域の住民にクリニックの存在を知ってもらい、新たな患者を集めることができます。その具体例は以下の通りです。
①テレビ・ラジオ
テレビCMは、最も有用な方法の1つです。テレビ番組の視聴者に届けることができ、全国的にブランドイメージを拡大させることができます。
とはいえ、膨大な費用がかかるため、通常は全国展開している医院でもない限りクリニックでは選択肢に入ってきませんが、ラジオにでもコメンテーターや相談役として出演できれば認知を高める方法ではあります。
②はがき・チラシ
ポスティングでは、リコールはがきが有効です。
リコールはがきとは、定期検診のお知らせなど、患者にリコールを促すことを目的に送るはがきを指します。地域密着型の場合、多くの人は家から近いクリニックを選択する傾向にあります。
特に、エリア内に同様の診療科がある場合など、競合が密集している場合は、新規集患だけでなくリピーター患者を逃さないための施策として適切な頻度でご来院していただくための仕組みづくりも有効となるでしょう。
手間や費用対効果の観点から歯科と比べて保険診療が中心となるクリニックではあまり活用されていませんが、再来院率の向上に繋がります。注意点としては、新規開院後では地域医師会との関係で、チラシの積極的な配布は制限されていることもあります。
③屋外看板・電車広告
屋外看板は交通量の多い道路沿いや信号待ちが発生する交差点に掲示することで、多く視認され、広告効果を期待できます。
また、駅ホームや改札付近の看板、電車看板などでも認知度を高めることもでき、ホームページやSNSへ誘導する点でも有用です。なお、正確な効果を数値として計測できない点がデメリットとして挙げられ、さらにスマホの普及により効果は以前よりも限定的となりました。
一般的に費用は高額となるため、広告目的を明確にし、設置場所もよく吟味する必要があります。
④地域情報誌
周辺の自治体のターゲット層の絞り込みから、それにあった種類の媒体を選択することで、認知を高めることが期待できます。また、広告だけでなく、記事として患者に有用な医療情報などを発信することで地域住民への貢献を通して医療機関としての信頼性を高めることにも繋がることでしょう。
⑤ダイレクトメール(DM)
ダイレクトメールでは、時節にあった予防情報やご案内をメールで発信できます。定期的なフォローアップはリピート患者の促進に効果的です。
ダイレクトメールを活用することで、次回の検診や治療の予約を促すリマインダーを簡単に送信できます。これにより、患者は定期的なケアの重要性を再認識し、予約を忘れることが少なくなりますが、最近はメールよりもLINEなどのSNSを活用したご案内の方が一般的となりました。
医療マーケティングの注意点
医療広告としてオフラインでもクリニックの集患対策を行う場合、厚生労働省が発表している「医療広告ガイドライン」に基づいた運用が必要です。
遵守するべき項目は多岐にわたる上、ガイドラインの内容は随時更新されるため、定期的に気を配りながら情報を把握することが必要になります。逸脱した表現にならないように注意しましょう。
クリニックで集患が上手くいかない原因
ところで、病院やクリニックで集患が上手くいかない原因は多岐にわたりますが、クリニックの雰囲気は悪くないのになぜか上手くいっていない代表的な問題点としては、「(まだ)認知度が低い」「差別化できていない」「口コミが少ない」「画像が少ない」「予約手段が少ない」ことなどが挙げられます。
これらの問題に対処することで、より多くの患者を集め、経営の安定化を図る解決に繋がる場合があります。具体的な例としては次の5つです。
①認知度が低い
新規患者を増やすためには、まずクリニックの存在を地域住民に認知してもらうことが不可欠です。認知度が低いと、そもそもクリニックの存在を知られず、訪れる患者が少なくなります。
地域に密着した地元メディアでの宣伝など、
認知度を高めるための積極的な取り組みが求められます。
②差別化できていない
他の病院やクリニックとの差別化ができていないと、患者が「家から近い方に通おう」などの理由で別のクリニックを選んでしまう可能性が高くなります。
そのため、専門的な診療科目や最新の治療法、患者への特別なサービスなど、他にはない強みを打ち出すことが重要となります。また、院内の雰囲気やスタッフの対応など、患者が快適に過ごせる環境を整えることも差別化の一環として効果的でしょう。
③口コミが少ない
口コミや評判は、新規患者にとってクリニックの信頼性を測る重要な要素です。患者からの口コミが少ない場合、その時点で信頼性が低いと判断されることがあります。
積極的に口コミを促進するためには、治療後に患者にフィードバックをお願いしたり、SNSでのシェアを呼びかけたりすることが効果的です。
また、良い口コミを得るためには、患者に満足してもらえる高品質な医療サービスの提供を基本とし、患者への何気ないお声がけなど、チームとして寄り添うクリニックを感じて頂けるための工夫があってのこととなるのは言うまでもありません。
④画像が少ない
テキスト情報だけでは、クリニックの雰囲気や信頼性に欠ける場合があります。ホームページやSNS、紙媒体に院内や院長、スタッフの写真があるのとないのとでは印象が大きく異なるのです。
また、クリニック(又は先生)の実績を示す症例や術例を紹介することで、クリニックの信頼性を高めることが可能です(ただし症例や実例が少ないと、逆に患者にとって信頼性が低いと感じられることもあります)。
その他にも施設の明るい雰囲気や笑顔のある挿絵や挿入写真を用いることで、分かりやすく潜在的に来院を促す効果も期待できます。加えて、学会発表や論文執筆などの活動を通じて、専門性をアピールするのもよいでしょう。
⑤予約手段が少ない
そもそも、予約というシステムがないケースもありますが、予約手段が限られていると、患者が予約を取る際に不便を感じることにつながります。特に電話受付のみで対応する場合、24時間対応は難しいため、患者が予約を取りづらい状況が生まれます。
そこでオンライン予約システムを導入することで、患者は24時間いつでも空き状況の確認や予約ができ、利便性が向上します。また、LINEやメールなど、様々な予約システムを用意することで、幅広い年齢層の患者に対応できるようになるでしょう。
クリニックの集患を成功させるポイントは?
オン・オフに限らず、病院やクリニックの集患を成功させるためには、患者のニーズに応えることが最も重要です。患者は医療機関へ単に処置を求めるだけでなく、治療方針の相談や不安の解消を求めて訪れます。
国内でも1997年より、医療従事者が患者のコンサルタントとなり、共に診察や治療の方針を決定するインフォームドコンセントが法的に義務化されました。限られた時間の中ではありますが、寄り添った説明や提案ができなければ、患者からの信頼を獲得することは難しく、患者様の満足度の向上は大きな課題です。
また、医者自身の対応にも注意を払うことが必要です。クリニックを経営する上で、受付や看護師との連携は欠かせません。医療機関はサービス業としての側面も持っており、受付や看護師の対応が患者の満足度やリピーターの増減に大きく影響します。例えば、初期集患が成功しても対応が悪い病院やクリニックには再び訪れたいとは思いません。
したがって、良い評判や口コミを集めるためには、集客施策と並行して施設スタッフの対応を確認し、必要であれば教育の機会を設けることが必要なのです。
さらに、集患施策を実施する際には、経営状況や院内の内装にも配慮する必要があります。患者が利用する施設の印象は、リピート率に直結します。たとえ新規患者が増えたとしても、内装や設備などが汚れているクリニックにはなかなかリピートしたいとは思いません。清潔で快適な環境を提供することで患者の満足度を高めることができるのです。
Webマーケティングとの組み合わせが重要
クリニックの安定経営のために集患は、地域での認知度を高め、適切な方法でアプローチすることが大切です。本記事で紹介したオフラインでできる事例を参考に、最適な施策を見つけて頂ければ幸いです。
また、オフラインマーケティングはWEBマーケティングと掛け合わせることで、集患をより一層促進することができます。ただし、診療科目や地域によってWEBマーケティングとの相性も異なるため、信頼のおける専門家に相談しながら進めて下さい。

執筆者 / 松崎 史朗
税理士法人TOTAL 開業支援部部長
宅地建物取引士合格 FP2級技能士 証券外務員一種 明治大学卒業
国際証券(現在の三菱UFJモルガンスタンレー証券)でリテール営業を経験後、外資系メーカーなどにも勤務。個人事業4年間を経て平成30年より税理士法人TOTAL再入社