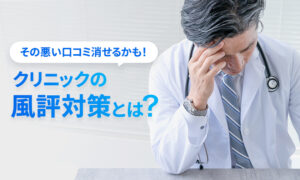クリニック開業のススメ
クリニックの開業の成功に向けた現場で役立つ実践的な情報を提供します。
クリニックのSNS活用術を解説!SNSの特性とは?

現代では、ほとんどの世代がスマートフォンを持ち、SNSが日常生活の一部となっています。医療機関では、SNSを活用することで集患やブランディングに大きな力を発揮します。適切に運用することで、クリニックの認知度や患者からの信頼を高めることが可能です。この記事では、SNS活用のメリットや具体的な成功事例を交えながら、クリニックに最適なSNS戦略を紹介します。
安定経営には患者数の確保が大事
クリニック経営では、保険診療収入、自由診療収入共に、診療単価と患者数に依存しています。このうち、診療単価は安定して推移するのが一般的ですので、ポイントは患者数となります。即ち、クリニックの安定経営のためには、一定の患者数を安定的に確保し、収入と利益を確保しつつ、経費や借入金の返済、生活費等のコストを賄うのが肝要となります。また、仮に現在、手元資金が潤沢であっても、患者数が減少傾向であるならば、将来的に経営が不安定になる可能性があります。そのため、継続的に効果的な集患施策を実施し、安定的に患者数を確保することがクリニック経営の重要なポイントの一つといえます。
以下では、安定的に患者数を確保する方策の一つとして、現在では一般的になっているSNSを活用した集患とクリニックのブランディングについてご紹介します。
マーケティングの目的は「認知」と「集患」
クリニックにおけるマーケティングの目的は、主に「認知度の向上」と「集患」にあります。従来のマーケティング手段である看板広告やテレビCMに加え、近年ではオンラインマーケティングが主流となり、特にSNSを活用した集患が注目されています。SNSを上手に活用することで、地域内での認知度向上や新規患者の獲得が期待できます。
SNSを活用するメリット
SNSの最大の魅力はリアルタイム性にあります。医療機関では急な休診や診療時間変更など、患者に重要な情報を迅速に伝える必要があります。SNSを活用すれば、これらの情報を即座に多くの患者へ届け、混乱や不安を軽減できます。また、視覚的な情報発信も可能なため、スタッフ紹介や設備、治療法の解説を写真や動画で伝え、クリニックの雰囲気や強みを分かりやすくアピールできます。特に新規患者にとっては、「どんなクリニックか」を事前に知ることで、安心して来院しやすくなります。
SNSの効果
SNSを活用することで、他のクリニックと差別化を図り、患者との信頼関係を強化できます。定期的に最新の医療情報や診療内容を発信することで、専門性をアピールし、リピーターの増加が期待できます。さらに、SNSの拡散力を活かして、新規患者の獲得にも繋がります。例えば、患者が投稿をシェアすることで、知人や家族にも情報が届き、信頼が広がります。特に予防医療や健康管理に関する情報は関心が高いため、拡散されやすいです。
成功事例:
地域密着型クリニックが「季節ごとの健康管理のポイント」や「生活習慣病予防の豆知識」を定期的に投稿したところ、患者の関心が高まり、フォロワー数が増加。投稿を見た患者が「健康診断を受けたい」「予防接種の予約をしたい」とクリニックに問い合わせるケースが増えました。一部の投稿が地域コミュニティのSNSグループでシェアされ、新規患者の来院に繋がる事例もありました。
SNS広告と伝統的な広告(電車広告など)の違い
◇リーチとターゲティングの精度
SNS広告の最大の強みはターゲティング精度です。年齢、性別、地域、興味関心などのデータを活用し、広告を届けたい層にピンポイントでアプローチできます。例えば、「〇〇駅周辺に住む30代女性」「健康に関心がある人」など、細かく設定して、関心の高いユーザーに情報を届けることが可能です。一方で、伝統的な広告(電車広告や看板広告など)は、ターゲット層を細かく絞り込むことが難しく、広い範囲に一斉に情報を届けるため、関心のない層にも表示される可能性があります。
◇コストと柔軟性
SNS広告は低コストで始めやすく、少額の予算で広告配信が可能です。また、クリック数や問い合わせ数に基づいて効果を分析し、柔軟に調整できます。これに対して、伝統的な広告は初期費用が高い傾向にあり、契約期間が決まっているため、柔軟な調整が難しいというデメリットがあります。
ドクター名で集患する時代
近年、クリニックの集患には医師個人の名前や専門性を前面に出すことが効果的とされています。SNSでドクター自身の経歴や専門分野、診療への想いを発信することで、患者からの信頼を得やすくなります。特に専門的な医学知識をわかりやすく解説する投稿は、医師の専門性と患者目線でのコミュニケーション能力を同時にアピールでき、効果的です。
成功事例:
皮膚科クリニックでは、院長が「肌トラブルの原因と対策」を解説する3分程度のショート動画を月に2回配信。医学的根拠に基づき、わかりやすい言葉で説明する姿勢が好評を博し、「動画を見て安心して受診できると思った」と、新規患者が増加。特に若年層の患者獲得に効果を発揮しました。
求人募集にも効果的
SNSは集患だけでなく、求人活動にも大きな効果を発揮します。従来の求人媒体では求職者が自ら情報を探さなければなりませんが、SNSでは普段利用しているプラットフォームで情報を届けることができます。クリニックの雰囲気やスタッフの働く様子を発信することで、「ここで働きたい」と思わせるブランディングが可能です。
各SNSの特性を理解して活用しよう
SNSを効果的に活用するには、それぞれのプラットフォームの特性を理解し、目的に合わせた運用が重要です。代表的な5つのSNSを例に上げて、特徴を解説します。
① X(旧Twitter):即時性の高い情報発信に最適
特性: 短文での投稿が基本で、情報の拡散性が高い。ハッシュタグを活用した情報整理が可能。
最適な活用法:
- 臨時休診や診療時間変更など、緊急性の高い情報発信
- 季節性疾患の流行状況や予防接種の案内
- 健康に関する簡潔なアドバイスやTips
- 医療ニュースへのコメントや解説
投稿頻度の目安: 週3〜5回(緊急情報は随時)
② Facebook:詳細な情報共有と地域コミュニティ形成に有効
特性: 短文での投稿が基本で、情報の拡散性が高い。ハッシュタグを活用した情報整理が可能。
最適な活用法:
- クリニックの理念や医師の診療方針の詳細な紹介
- 健康セミナーやイベントの告知と報告
- 地域の健康課題や医療情報の共有
- 詳細な症例解説(個人情報に配慮した形で)
投稿頻度の目安: 週2〜3回
③ Instagram:視覚的な訴求力でブランディングに最適
特性: 写真や短い動画が中心で、視覚的な印象が強い。特に20〜40代の女性ユーザーが多い。
最適な活用法:
- 院内の雰囲気や設備、スタッフの紹介
- 治療のビフォーアフター(同意を得た上で)
- 健康管理のコツを視覚的に解説
- 医師やスタッフの日常業務の一コマ
投稿頻度の目安: 週2〜4回
④ LINE:患者との直接的なコミュニケーションに有効
特性: 個別メッセージや一斉配信が可能で、開封率が高い。幅広い年齢層に利用されている。
最適な活用法:
- 予約の確認や変更の案内
- 健康情報や季節の注意点などの定期配信
- 予防接種の時期や健康診断の案内
- 個別の質問や相談への対応(診療範囲内で)
配信頻度の目安: 月1〜2回(過度な配信は避ける)
⑤ YouTube:詳細な医療情報解説やクリニック紹介に最適
特性: 長時間の動画コンテンツが可能で、検索エンジンとしての側面も強い。
最適な活用法:
- 疾患や治療法の詳細解説
- クリニック施設の詳細ツアー
- 医師による健康講座や相談会のアーカイブ
- 日常的な健康管理のハウツー動画
投稿頻度の目安: 月1〜2回(質を重視)
医療機関のSNS運用における注意点と法的配慮
医療広告ガイドラインを遵守することは必須です。治療効果の誇大表現や未承認医薬品の宣伝禁止など、法的な規制を守りつつ、患者プライバシーの保護にも十分な配慮が必要です。SNSでの情報発信においては、投稿前のチェック体制や、患者情報漏洩の防止策をしっかりと構築しましょう。
オフラインマーケティングとの組み合わせが重要
クリニックの集患は、地域での認知度を高め、SNSと看板広告などのオフラインマーケティングを組み合わせることでさらに効果的に促進できます。診療科目や地域に応じて、最適なマーケティング手法を選ぶことが重要です。専門家に相談し、最適な施策を実施しましょう。

執筆者 / 樺島 大悟
税理士法人TOTAL 開業支援部
駒澤大学卒業後 新卒で税理士法人TOTALへ入社
入社直後より医療関係の顧客を中心に税務会計コンサルティングを行う。その中で、医療開業の面白さに惹かれ、現在はクリニックの開業支援に携わる。