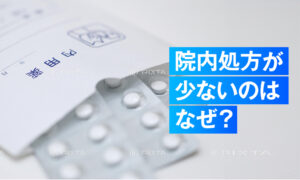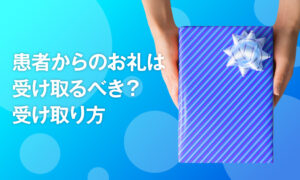クリニック開業のススメ
クリニックの開業の成功に向けた現場で役立つ実践的な情報を提供します。
医師として知っておくべき「応召義務」とは?
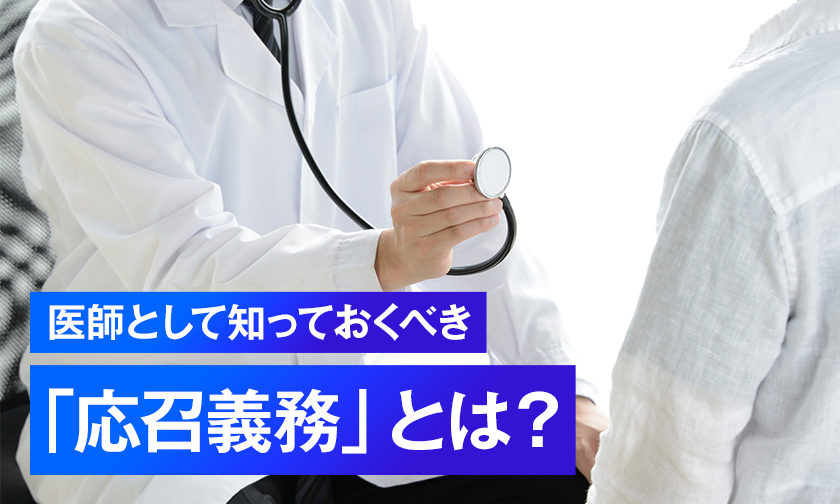
医師には「応召義務」という重要な役割が法律で定められています。これは、患者からの診療の求めに応じて適切な医療を提供する義務を指します。しかし、すべての場合においてこの義務を負うわけではなく、「正当な理由」が認められる場合には例外が適用されます。この「正当な理由」とはどのような状況を指すのでしょうか?
この記事では、医師が知っておくべき応召義務の基本から、義務を免れるケースとされる「正当な理由」、さらに発熱外来での応召義務の取り扱いや疑問について解説します。
応召義務(おうしょうぎむ)とは?
応召義務とは、1948年7月30日に交付された医師法19条(歯科医医師法19条)で定められている医師の義務です。医師法19条では、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められています。つまり、患者が診療や治療を求める場合、医師は正当な理由なしに断ることはできません。正当な理由とは、例えば専門外の治療で対応が難しい場合や、診療体制の限界を超える場合などが該当します。
また、医師を雇用する医療機関についても、医師個人の応召義務と同様に正当な理由なく診療を拒んではならないと規定されています。
応召義務を負う必要がない「正当な理由」
医師は正当な事由があれば、診療や治療を拒否しても違法には当たりません。しかし、「正当な事由」に該当するかどうかの判断が難しいのも事実です。医師法が公布された1948年から現在に至るまで、医療を取り巻く環境や医師の労働状況は大きく変化してきました。
こうした背景を踏まえ、厚生労働省は2019年12月25日、各都道府県知事宛に「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」という通達を発出しました。この通達では、正当な理由がない限り診療や治療を拒否することは認められないとする従来の応召義務の基本原則を維持しつつ、正当な理由についてより具体的な指針が示されています。
専門外の疾患である場合
医師が患者の求める診療内容に関する十分な専門知識や技術を有しておらず、適切な診療が提供できない場合は、正当な理由として認められます。また、専門の疾患だったとしても、医師を雇用する医療機関に必要な治療を行える設備や器具がそろっておらず、適切な検査や処置ができない場合も正当な理由に該当します。
診療時間外の場合
診療時間外の場合、診察や治療を拒んだとしても原則として公法上・私法上の責任を問われることはありません。
ただし、生命に関わるような緊急事態(例: 心停止、大量出血、呼吸困難など)の場合は、診療時間外でも応召義務が適用される可能性もあります。また、他の医療機関が診療を拒否し、患者が対応可能な医師に頼らざるを得ない場合なども該当します。この場合、診療時間外でも適切な対応を検討する必要があります。医師には患者の命を守る責任があるため、緊急対応が可能な医療機関を紹介するなど、適切な対応が求められます。
迷惑行為を受けた場合
厚生労働省の通達では、患者との信頼関係が失われた場合や迷惑行為がある場合には、診療を拒否する正当性が認められる場合があるとされています。例えば、医療従事者に対する暴言や暴力、セクハラ、他の患者やスタッフへの妨害、不必要な薬や検査の強要、治療内容への理不尽なクレームの繰り返しなどが該当します。
最近では「モンスターペイシェント」による問題が増え、医療従事者が精神的に追い込まれるケースも少なくありません。医療機関は、問題行為への対応やトラブル防止策を強化し、信頼関係を保ちながらも、医療従事者が安心して業務に専念できる環境を整えることが求められています。
医療費が不払いの場合
患者に支払能力があるにもかかわらず、悪意を持ってあえて支払わない場合には、診療拒否は正当化されます。
例えば、保険診療において、特段の理由なく自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであると推定されることもあります。
ただし、患者が保険に未加入の場合、その理由だけで医療費の支払い能力が不確実であるとして診療拒否することは正当化されません。
自由診療においては、支払い能力がない患者に対して診療拒否は正当化されます。
発熱外来で応召義務は発生する?
発熱外来における応召義務違反に該当するかどうかは、感染症の種類や状況によって異なります。例えば、感染症法の分類や国の方針に基づき、対応が特定の医療機関に限定される場合や、医療機関の設備や人員の制約が正当な理由として認められる場合があります。そのため、どのように対応すべきかを判断する際には、最新の国の通達やガイドラインを確認することが重要です。
新型コロナウイルス感染症と応召義務
新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年、厚生労働省は「発熱や上気道症状がある」という理由だけで診療を拒否することは、正当な理由には該当しないと通達しました。ただし、感染症法の分類により対応可能な医療機関が限定されていた時期もあり、例えば新型コロナウイルスが2類感染症相当とされていた時期(2023年5月7日以前)は、特定の医療機関以外で診療を拒否しても応召義務違反にはなりませんでした。
しかし、2023年5月8日以降、新型コロナウイルスは5類感染症に移行し、発熱や感染症が疑われる患者に対する診療は通常の医療機関でも求められるようになりました。そのため、特別な理由がない限り、発熱外来でも診療を拒否することは応召義務違反となります。診療が困難な場合でも、他の医療機関への案内など適切な対応を取ることが求められます。
応召義務に違反するとどうなる?
医師の応召義務は医師法で定められていますが、違反した場合の刑事罰は規定されていません。応召義務違反により医師免許の取り消しや業務停止などの行政処分が下される可能性はありますが、2018年時点ではそのような事例は確認されていません。一方で、診療を拒否した結果、患者が損害を受けた場合、医師や医療機関に対して民事訴訟を提起される可能性はあり、法的責任を問われることがあります。
保険証を忘れた患者の診察は断れる?
保険証を忘れた患者の診察を一律に断ることは、原則として応召義務に反する可能性があります。医師法第19条では、正当な理由がない限り診療を拒否することを禁じているため、保険証の提示がないという理由だけで診療を拒否するのは適切ではありません。
ただし、保険証がない場合、その日の診療費は一旦全額自己負担で支払ってもらい、後日保険証を持参してもらうことで保険診療分を清算する対応が一般的です。また、患者が保険証を持参できない事情を丁寧に確認し、適切な案内を行うことが求められます。診療拒否ではなく柔軟に対応することで、医療機関としての信頼性を保つことが重要です。
応召義務か判断できない場合は専門家に相談
応召義務は、医師が患者に適切な医療を提供する責務を果たすための基本的な指針です。しかし、時代や医療環境の変化により、その解釈や適用には新たな視点が求められています。そのため、最新の国の通達やガイドラインを常に確認し、適切な対応を心がけることが重要です。また、判断が難しい場合には法律の専門家に相談することをお薦めします。
応召義務というテーマは、場合によっては医療機関に対する地域の信頼性や評判に悪影響をもたらすこともあります。トラブルを未然に防ぐために、各種情報を得て適切に対応して頂きたいと思います。

執筆者 / 三田村 清幸
税理士法人TOTAL 医業経営コンサルタント
岩手大学工学部卒業
理数系の教育分野で海外勤務後、我が国初の医業経営コンサルティング専門企業の設立に参加。海外・国内の病院コンサル事業に従事、同社は国内最大手企業に成長。役員を経て、2020年に税理士法人TOTAL入社