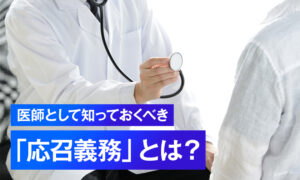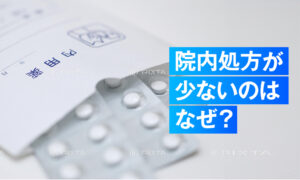クリニック開業のススメ
クリニックの開業の成功に向けた現場で役立つ実践的な情報を提供します。
患者からのお礼、医師は受け取るべきか? 受取り方
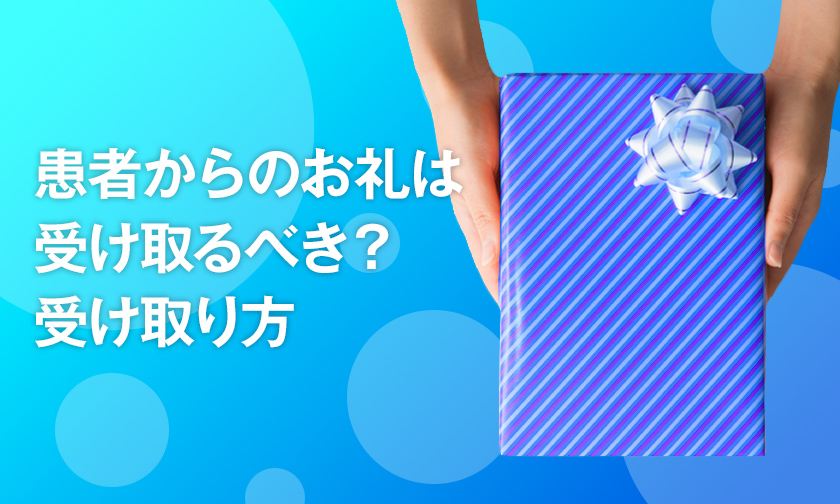
病院やクリニックにおいては、しばしば患者からお礼の申し出があります。患者からすれば、病気や怪我から回復できた感謝の気持ちを、どうしても医師に伝えたい、形で表したいという思いが強いのも事実です。
ではその際、医師はお礼を受け取るべきなのか、受け取るとしてどのように受け取るのが良いか、悩まれる医師の方も多いのではないでしょうか。一方、患者は患者で、特に命に関わる治療や大きな手術の後では、感謝の気持ちをどのように伝えられるか、どのような謝礼が良いか、その渡し方などについて不安になることもあるでしょう。
本記事では、医師へのお礼の持つ意味、医師の受け取り方、お礼の適切な形式、そして受け取り方のマナーについて解説します。患者の素直な気持ちを尊重し、上手に患者に対応することで、患者との良い関係を築くヒントにしてください。
患者からのお礼について、各方面の見解
日本医師会では、「医の倫理の基礎知識2018年版」の中で、患者や家族からの謝礼について以下を結論として、原則的に患者・家族に対して謝礼を要求したり、患者から受領したりすることを禁じています。
- 原則、患者からの謝礼はもらわない。
- 特に、病院の規則などでもらわないとされている場合はもらわない。
- 患者・家族の素直な謝意と感じられたらもらうこともありうる。
- その場合も、常識的な範囲であること
- 物品をもらったことで、患者を差別するようなことはあってはならない。(受取った側が利益誘導とみなされてはならない)
また、民間の総合病院などの大きな病院では、待合室など目立つところに「お心付けは受けとれません」という貼り紙で告知する他、就業規則や雇用契約書で患者からの謝礼の受領を禁止しているケースが多く見られます。
公立病院の場合には当然ながら、こうした心付けなどの謝礼を受け取ると、公務員としての倫理規程に抵触することになりますので、心付けは一切禁止としています。
以上の例から、総じて医師へのお礼については否定的な見解が多くみられます。
患者との「コミュニケーション」の観点から、お礼の位置付け
前述の通り、医師は、原則的に患者からのお礼は受取らないというルールが一般的ですが、日本医師会の結論で指摘している通り、「患者・家族の素直な謝意と感じられたらもらうこともありうる」として、例外を認めています。
これについては、医師と患者のコミュニケーションという観点から理解できるのではないでしょうか。
即ち、現在の医療は、「患者の受診の申し出を受けて、医師は診察・診断・治療の医療技術を提供する」という従来の役割を超えて、患者のQOL(生活の質)の向上に貢献する役割へと変化しています。そのため、ドクターは診療現場において、患者と積極的にコミュニケーションを図り、患者は少しでも医師に近づこうとしてコミュニケーションに応じています。
このような環境の中で、感謝の気持ちを医師に伝えたいという患者の思いも自然発生的なことに思えます。特に、大きな手術や特別な対応を受けた場合には、その想いは更に強くなることでしょう。
現在の医療は、医療機関で提供される治療やケアがすべて保険診療や規定内のサービスであるため、追加の費用や、医療費用を賄うためのお礼は必要ではありません。そのため、医療費用以外に、必須ではないものの、患者の純粋に感謝の気持ちを伝えたいという思いがお礼という形になってくるものと考えられます。
金銭でのお礼が最適か? 相場とリスク
では、勤務している医療機関で金品受取の禁止がない、あるいは就業規則での禁止条項がない状況で、医師が患者の素直な気持ちを理解しつつ、患者からのお礼の申し出を受ける場合、どのようなお礼を受け取るのが良いでしょうか。
ここでは、お礼が金銭の場合を考えてみます。
金銭でのお礼の相場は、1万円から5万円が一般的とされていますが、一方、金銭はトラブルの原因になりやすいとも言われています。そのため、そのことを想定する医師の中には、最初から金銭の受け取りを拒否する方もおられます。
また、患者から金銭でのお礼の申し出を受けた後、お断りや拒否することがあれば、医師と患者の関係が気まずくなり、その結果、診療に影響する事態も考えられます。従って、患者から金銭でのお礼の申し出があった場合、可能ならば、金銭を避けて金銭以外の他の方法を選ぶよう患者に提案することも、対応策の一つではないでしょうか。
では、品物でのお礼が良いか?
品物でのお礼は、金銭と比べて医師も受け取りやすいと見られています。
特に、日常的に使うものや、医療現場で役立つものであれば、医師に喜ばれることが多いようです。例えば、上質なお菓子や飲み物、文房具類などが人気となっていますが、ただし、高価過ぎるものは、逆に負担に感じることになりますので、受け取る際には注意が必要でしょう。
一般的にクリニックは地域密着型が多いですから、一度品物を受け取ると、その品物が医師の好みと判断され、あるいはクリニックのスタッフの口コミを通じて、地域の患者に広まる可能性があります。
一方、贈る側の患者は、普通のお中元やお歳暮と同じく、贈る品物に「相手方の好みを考慮した特別感」を持たせ、さらに印象を良くしようとするでしょう。たとえば、地元の名産品や季節感のある贈り物などです。
このような背景がある中で、お礼の品物の受取についても、やはり地域の状況や、患者心理を考慮して対応することが重要となりそうです。
お礼を受け取るとして、その場合のマナーとタイミングや、注意すべきこと
もし、お礼を受け取ることになった場合、その際にもマナーとタイミングを意識することが大切です。
医師は忙しい業務の合間を縫って、受け取りに対応することになるため、診察時間中や急患対応中は避けるべきです。最適なタイミングとしては、診療が終わった後や手術後の面会時など、医師が比較的落ち着いているときが望ましいと言えます。
また、お礼を受け取る際には、マナーとタイミングを意識することも大切です。
医師が診察時間中や急患対応中に、患者からのお礼の申し出があった場合、医師ならずとも嫌な顔になりがちです。その場合には、無下に断らず、診療が終わった後や手術後の面会時など、医師が比較的落ち着いているときに応対できる旨を、スタッフを通じて患者にお伝えするのが良いでしょう。また、受け取る際には、患者の感謝の気持ちを素直に受け止め、患者をリスペクトする態度を心がけることも大切です。
当然ですが、お礼を受け取る際には、他の患者から見えない場所で行うよう、注意してください。不特定多数の人がいる場面でお礼を受け取ると、他の患者に不快な思いをさせて、不公平だと感じさせる可能性があります。そのため、受け取る際には、診察室や個室など、周囲の目に触れない場所で行うよう心がけたいものです。
くれぐれも横柄な態度で、見下すような仕方でお礼をいただくのは止めてください。せっかくの医師への感謝の気持ちが、医師への反感に変わりかねないことになり、医師や医療機関にとって大きな損失になります。
多様な謝意の表現方法
金銭や品物以外で感謝の気持ちが通じる方法も多く存在します。たとえば、手書きの感謝状や手紙は、医師にとっても心に残る贈り物となることがあります。具体的にどのような点に感謝しているか、患者自身の言葉で伝えることができれば、医師にとっても大きな励みになるでしょう。
また、医療機関の公式アンケートやレビューへの感謝のコメントも一つの方法です。これにより、医師やスタッフの努力が広く評価される機会になるでしょう。特にSNSや口コミサイトでのコメントは、多くの人の目に留まるため、感謝の意が共有できる良い手段です。感謝の気持ちが形にされることは大切ですが、患者からの謝意の表現には多様な方法がありますこと、ご理解ください。
まとめ(患者からの感謝の受け止め方)
日本の文化においては、お中元やお歳暮の習慣にみられる通り、贈る側と贈られる側の双方の関係を維持し、また感謝を表現するコミュニケーションの方法として、贈り物文化が古くから根付いています。
すなわち、医療現場においても同様に、患者から医師への感謝の表現方法として、医師へのお礼、あるいは「お心付け」という形で発現されているものと考えられます。
もちろん、これは法的に義務付けられているわけではありませんし、必須でもありませんが、この習慣は文化となって、あくまで患者やその家族が自発的に行う任意の行為として広く認識されています。
重要なのは、感謝の意を受け取る行為が、医療の質や患者との関係性に影響を及ぼすことがあってはならないことです。それが前提となって、「患者の感謝の気持ちは、お礼の種類に寄らない」という原則が生きてきますので、このことは受け取る側の医師がしっかりと認識すべきではないでしょうか。
最後に、謝礼にも税金がかかるか?
謝礼を受け取る際には、税法上の取り扱いについても注意が必要です。
一般的に、謝礼は職務の対価と見なされることが多く、「雑所得」又は「事業所得」に分類されます。そのため、他の所得と合算して申告が必要になる場合があります。
ただし、謝礼の金額相当額によっては「受贈」として扱われ、一定の金額を超える場合には贈与税の対象となる可能性もあります。
謝礼の申告をしていない、または正しく申告できているかご不安な場合は、お近くの税理士に相談されることをおすすめします。

執筆者 / 三田村 清幸
税理士法人TOTAL 医業経営コンサルタント
岩手大学工学部卒業
理数系の教育分野で海外勤務後、我が国初の医業経営コンサルティング専門企業の設立に参加。海外・国内の病院コンサル事業に従事、同社は国内最大手企業に成長。役員を経て、2020年に税理士法人TOTAL入社